皆さん、こんにちは!てつやです。
定年後の「やってみた!」挑戦はまだまだ続いています。今回は“雑記帳”として、最近の心の動きについて少しお話しさせてください。
以前、このブログで岩尾俊兵さんの『世界は経営でできている』という本をご紹介しました。家庭を”経営”と捉えることで、妻との日常的な関係がずいぶんと温かいものに変わった、というお話でした。
▼前回『世界は経営でできている』をご紹介した記事はこちらです。
定年後の人生は“経営”だった?60代の私が『世界は経営でできている』で夫婦関係を見つめ直した話
しかし、そんな風に良い方向へ向かっていると感じる一方で、心のどこかに拭いきれないモヤモヤがあったのも事実です。そして、その正体を教えてくれたのが、今回ご紹介するもう一冊の本でした。
タイトルは、『「やりたいこと」はなくてもいい。』。正直、「これは目標を探す若い人向けの本だろう」と、最初は自分に関係ないと思っていました。
ところが、この本が「家庭経営」の次のステップに進むための、非常に重要なヒントをくれたのです。今回は、そんな私の個人的な「気づき」の続編です。
きっかけは「自分には関係ない」と思っていた一冊の本
『世界は経営でできている』を読んで以来、私は自分の人生や家庭を「経営」という視点で見るようになりました。そのおかげで、日々の小さな対立は減り、穏やかな時間が増えたのは間違いありません。しかし、一方でこんな思いも芽生えていました。「さて、この『我が家』という会社を、これからどっちの方向に進めていこうか?」と。
そんなことを考えていたある日の午後、次の車中泊の目的地でも探そうかとノートパソコンを開き、定年後の生き方に関する記事などを読んでいた時のことです。ふと、ダイヤモンド・オンラインに掲載されていた、しずかみちこさんという方の記事が目に留まりました。
正直に言います。最初の印象は「自分には関係ない本だな」でした。 「やりたいこと」探しなんて、就職や転職を控えた若者が悩むこと。もう十分に働き、人生のレールもおおよそ見えている自分には、縁のないテーマだと思ったのです。
しかし、記事を読み進めていくうちに、ある一節に目が釘付けになりました。
本書では自分の道が見えてくるためのSTEP1は「世界を広げる」こと、その中でも「世の中の仕組みを知る」ことから始めると書きました。
(中略)
それが世界を「縦」と「横」に広げる挑戦です。 まず「縦」の挑戦について説明します。 これは、「自分と同じ場所にいる人でも、違う価値観を持っている」と知ることで視野を広げることです。
(出典:ダイヤモンド・オンライン)
「……これだ!」と、思わず声が漏れました。
「自分と同じ場所にいる人でも、違う価値観を持っている」。この言葉が、ずっと心にあったモヤモヤの正体を解き明かし、すとんと腑に落ちたのです。そして、真っ先に頭に浮かんだのは、毎日同じ家で、同じ食卓を囲んでいる「妻」の存在でした。
長年連れ添い、定年後は四六時中「同じ場所にいる」私たち。それなのに、なぜか会話が噛み合わないことがある。その理由が、この記事の一節に凝縮されているように思えたのです。
「これって、単なる自分の価値観探しの話じゃない。夫婦という共同経営者が、お互いの根っこにある価値観を理解しながら、会社のビジョンを共有していく話なんじゃないか?」
この記事が、しずかみちこさんの著書『「やりたいこと」はなくてもいい。』の内容を元に編集されていると知り、私はすぐに本を注文しました。それは、私の「家庭経営」が、次のステージへ進むための大きな発見の始まりでした。
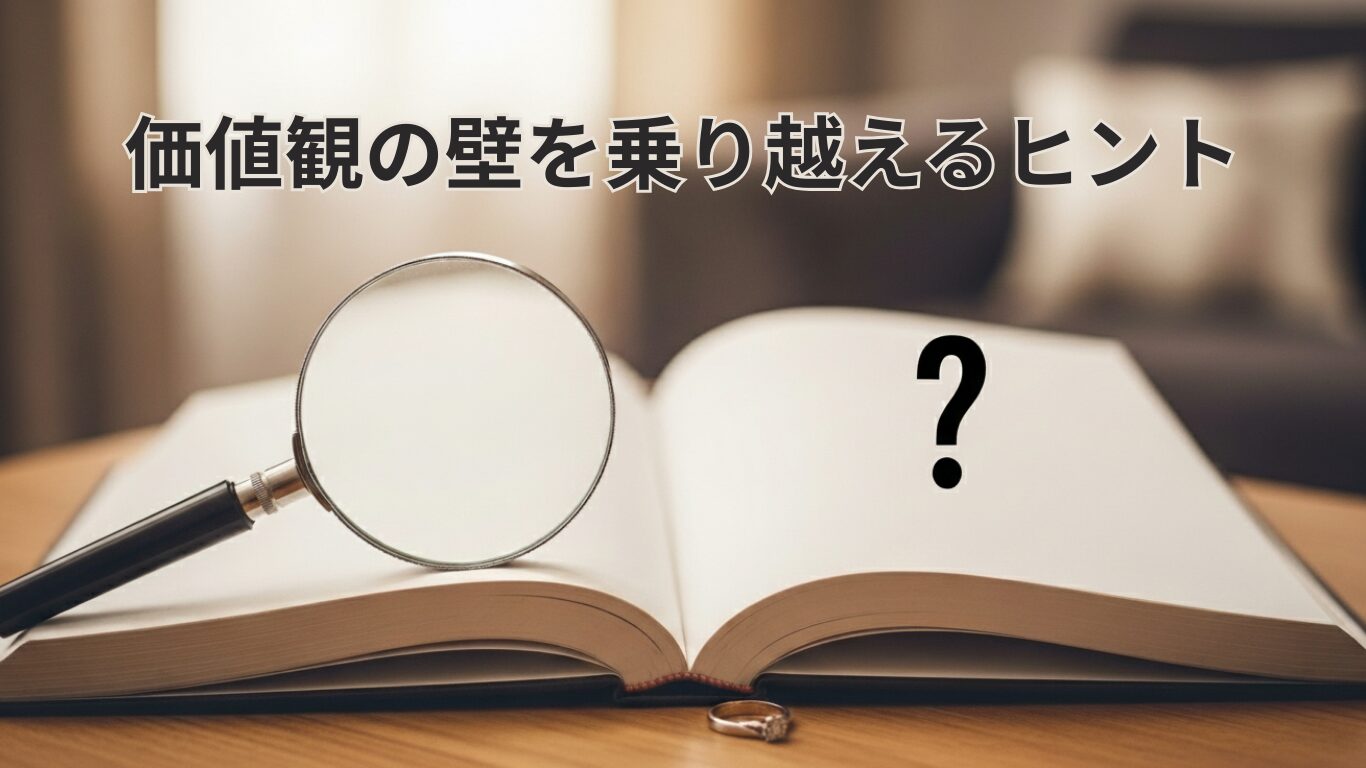
「わかっているつもり」だった価値観の多様性
思い返せば、私は合併の多い会社で長年勤めてきました。昨日まで違う会社だった人たちと机を並べ、文化も仕事の進め方も全く違う中で、一つのチームとして成果を出していく。そんな毎日でしたから、「価値観は人それぞれで、多様である」ということは、頭では理解していたつもりでした。
ですから、自分は「価値観の多様性」については、同世代の誰よりも理解がある人間だと、どこかで自負していました。いわば「異文化コミュニケーション」のプロだとすら思っていたのです。
しかし、この本を読んで、その自信はもろくも崩れ去りました。 私は、その視点を家庭に持ち込めていただろうか?仕事ではあれほど「相手の背景を理解しよう」「なぜ彼はそう考えるのだろう?」と努めていたのに、家庭ではどうだったか。
「なんで妻は、私の楽しみをわかってくれないんだ」
「どうしてそんなに心配ばかりするんだ」
そう、家庭での私は、相手を理解しようとするのではなく、自分の価値観を押し付け、「わかってくれない」と不満を募らせるばかりだったのです。まさに「灯台下暗し」。最も身近で、最も大切なパートナーである妻の価値観を、一番理解しようとしていなかった自分に気づき、愕然としました。
この本が改めて教えてくれたのは、以下の2つのシンプルな事実でした。
- 同じ場所にいる人(=家族)でも、価値観は違うという事実
- 自分の世界を広げる(=新しいことに挑戦する)ことは、他者の価値観を理解するためにも不可欠であること
この気づきは、私が漠然と抱いていた「人生後半戦は、後悔しないように生きるぞ!」という決意に、確かな輪郭と自信を与えてくれるものとなりました。
最も身近な異文化 ― 「攻める私」と「守る妻」の価値観の違い
さて、その新しい視点で改めて妻との関係を見つめ直してみると、『世界は経営でできている』を読んで改善されたはずの私たちの間に、依然として横たわる大きなテーマが見えてきました。
確かに、「ありがとう」という感謝の言葉は増えました。家事を手伝うのも当たり前になりました。日常の空気は、間違いなく良くなったのです。しかし、いざ「これからどう生きたいか」「休日は何をして過ごしたいか」という、少し大きな話をしようとすると、途端に会話が噛み合わなくなる。
その根本原因こそが、この本が教えてくれた「価値観の違い」だったのです。
私は、健康でいられる今のうちに、これまで我慢してきたことを全部やり尽くしたいという「攻めのタイプ」です。車中泊で全国を巡ったり、新しい趣味に挑戦したり、とにかく後悔したくない一心です。
一方、妻は心配性で、何事にも慎重な「守りのタイプ」です。「健康に悪いものは食べない」「無理な運動はしない」「危険そうな旅行は控える」と、健康第一で堅実な生活を志向しています。
どちらが正しいという話ではありません。これは、お互いが無意識に掲げている「人生の究極の目的」が違う、ということなのです。
もしかすると、読者の皆さんの中にも、パートナーとの間で「なぜ分かり合えないのだろう?」と感じた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。その原因は、コミュニケーション不足ではなく、そもそもの「価値観の違い」にあるのかもしれません。
私は「体験や挑戦による充実感」を求め、妻は「平穏と安心による幸福感」を求めている。この根本的な価値観が違うのだから、表面的なコミュニケーションを改善しただけでは、いつか必ず大きな壁にぶつかる。それが、私が感じていたモヤモヤの正体でした。
答えではなく「問い」を見つける旅へ
重要なのは、この本が「こうすれば夫婦仲が円満になります」といった、安易な解決策を示してくれたわけではない、ということです。もしそうだったら、きっとここまで私の心には響かなかったでしょう。
この本が私にくれたのは、「家庭経営」を次のステージに進めるための「正しい問い」でした。
これまでの私の問いは、「どうすれば妻を説得して、自分のやりたいことを理解してもらえるか?」でした。でも、今は違います。
「価値観が全く違う私たちが、お互いを尊重しながら、二人で心から納得できる『共通の経営ビジョン(究極の目的)』を見つけるには、どうすればいいだろうか?」
この問いに変わったのです。
答えはまだ見つかっていません。でも、正しい問いを立てられたことで、妻との対話が少し変わってきた気がします。私たちの人生後半戦の「やってみた!」挑戦は、どうやら夫婦の新たな関係づくりになりそうです。
読者の皆さんも、少しだけ考えてみてください。ご自身とパートナーは、「攻めのタイプ」でしょうか、それとも「守りのタイプ」でしょうか。
まとめ
今回は、前回の『世界は経営でできている』に続き、一冊の本から得た「夫婦関係のヒント」についてお話しさせていただきました。
『経営本』が日常の行動レベルでの改善のヒントをくれたとすれば、今回の『価値観本』は、その根底にある意識レベルでの相互理解の重要性を教えてくれました。この二つは、車の両輪のようなものなのかもしれません。
「定年後の夫婦は、第二の人生を共に歩む共同経営者だ」なんて言われますが、まさにその通りだと感じています。そして、良い経営のためには、まずはお互いのビジョン(価値観)をしっかりと共有し、尊重し合うことから始めなければいけなかったのですね。
「やりたいこと」が明確に見つからなくても、目の前にいる大切な人の価値観を、一つの「異文化」として尊重し、理解しようと努めてみること。それが、結果的に自分の凝り固まった世界を広げ、人生をより豊かなものにしてくれるのかもしれません。
もし、私と同じように、長年連れ添ったパートナーとの価値観の違いに、少しだけ戸惑いや寂しさを感じている方がいらっしゃったら、この経験が何かのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。
さて、次回はまた楽しい車中泊の旅の記録に戻ります!次はどこへ行こうか、妻と「対話」しながら決めてみることにします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
▼今回取り上げました本にご興味がある方は以下からどうぞ
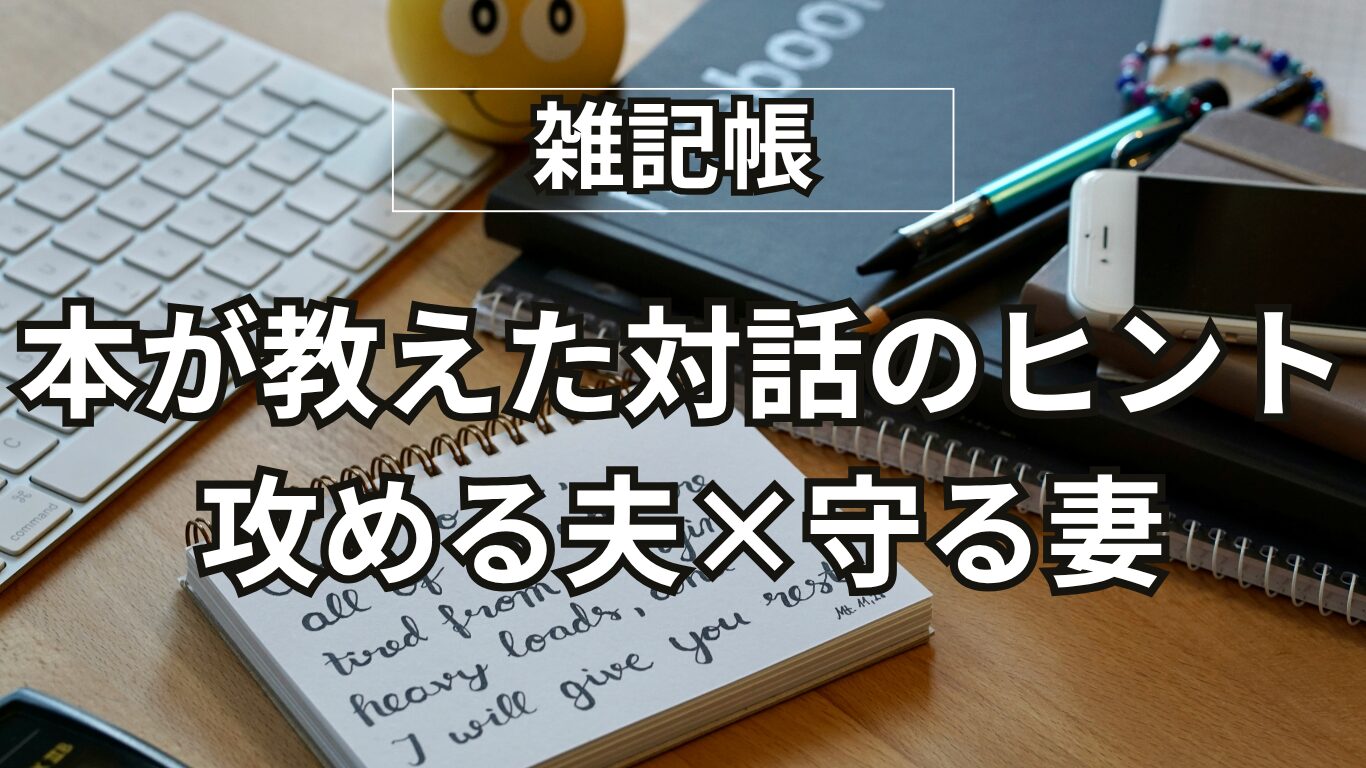



コメント