「8時10分前」。この言葉を聞いて、あなたは何時を思い浮かべますか?
こんにちは、てつやです。定年後の「やってみた!」挑戦記、今回は日々の気づきを綴る「雑記帳」をお届けします。長年の常識が覆され、思わず「まさか!」と驚いたエピソードです。
先日、何気なく読んでいたネット記事で、「8時10分前」という言葉の解釈が世代によって全く違うという話題が目に入りました。長年、当たり前のように「7時50分」だと思って生きてきた私にとって、それはまさに青天の霹靂。
この記事では、なぜこんなにも時間の感覚にズレが生まれるのかを紐解きながら、現役時代を振り返って感じたコミュニケーションの難しさ、そしてこれからの人付き合いで大切にしたいことについて、私の気づきを綴ってみたいと思います。

はじめに
当ブログへようこそ。
このブログは、定年後の私が「ブログ開設」を皮切りに、「車中泊」や日々のことなど、やりたかった事に挑戦する様子を綴っています。
今回は少し箸休めとして、日々の気づきを綴る「雑記帳」の記事です。テーマは「時間」にまつわる言葉なのですが…皆さんは、「8時10分前」と聞いて、何時を思い浮かべますか?
まさか、この言葉が通じないなんて!何気ない日常に潜んでいた「世代間の言葉の壁」
とある日の朝食後、のんびりとコーヒーを飲みながらスマホを眺めていた時のこと。いつものようにニュースサイトを巡回していると、ある記事のタイトルが目に飛び込んできました。
「え、どういうことだ?」
思わず声に出してしまい、向かいに座っていた妻が「どうしたの?」と顔を上げます。「いや、この記事だよ。『8時10分前』が通じないなんて書いてある」と、興奮気味にスマホの画面を見せました。
すると妻は、少し笑いながらこう言ったのです。「ああ、それ!私もテレビで見て、本当に驚いたのよ。私たちにとっては『7時50分』以外に考えられないのにねぇ」と。
なんと、妻はすでにこの話題を知っていたのです。二人して「当たり前だと思っていたことが、もう当たり前じゃないんだねぇ」「時代が変わるって、こういうことなのかしら」と、顔を見合わせてしまいました。
自分が半世紀以上も当たり前に使ってきた言葉が、もはや「共通言語」ではないのかもしれない。この事実に、私は言いようのない不安と、同時に強い興味を覚えたのです。
「8時10分前」論争!あなたは7時50分派?それとも…?
この衝撃的な事実を知ってから、私なりに少し調べてみました。すると、この「8時10分前」問題は、ネット上では定期的に話題になる「世代間ギャップ」の代表例であることが分かってきました。
アナログ時計世代の当たり前「8時の10分前だから7時50分」
まず、私と同じか、それより上の「昭和世代」にとって、「8時10分前」は議論の余地なく「7時50分」を指します。これは、私たちの頭の中にアナログ時計(針の時計)が染みついているからに他なりません。
長針が「50」を指し、短針が「8」の少し手前にある。その盤面を思い浮かべれば、「8時まで、あと10分」という情景が直感的に理解できます。「〇時〇分前」という表現は、目的地(〇時)までの残り時間を視覚的に捉える、アナログ時計ならではの文化が生んだ言葉と言えるでしょう。私たちは、数字を読むのではなく、針が作る「角度」や「位置関係」で時間を感覚的に把握してきたのです。
デジタルネイティブ世代の感覚「それって何時ですか?」
一方、生まれた時からデジタル表示が当たり前だった若い世代、いわゆる「デジタルネイティブ」にとっては、この感覚が通用しないようです。
彼らにとって時間は、「07:50」や「08:10」といった数字の羅列で認識するもの。そこに「前」という曖昧な概念が入る余地は少ないのかもしれません。
ある調査では、若い世代に「8時10分前」は何時かと尋ねたところ、
- 私たちと同じ「7時50分」と答える人
- 「8時10分頃」という曖昧な時間と捉える人
- 「全く意味が分からない」と答える人 に分かれたそうです。中には「8時を10分過ぎた時間」と解釈する人もいるとか…。
「え、なんでそうなるの?」と不思議に思うのですが、彼らからすれば「7時50分なら、なぜ素直にそう言わないのか?」という至極もっともな疑問が返ってくるのです。確かに、デジタルで正確な時刻が瞬時にわかる現代において、「〇分前」という表現は、もはやノスタルジックな、あるいは少し不親切な言い方なのかもしれません。
なぜ解釈が分かれるのか?背景にある時計の進化と時間の捉え方
この解釈の違いは、単なる「言葉のあや」ではありません。その背景には、私たちの生活環境の劇的な変化があります。
- テクノロジーの変化:
アナログ時計からデジタル時計へ。そして今はスマホの画面で時刻を確認するのが主流です。常に正確な数字が表示される環境では、「〇分前」という感覚的な表現は必要とされなくなりました。 - 教育の変化:
私が子供の頃、時計の読み方はアナログ時計で学びました。しかし、今では最初からデジタルで教える学校もあると聞きます。 - コミュニケーションの変化:
メールやチャットでのやり取りが増え、「〇〇時〇〇分に会議室集合」のように、誤解の余地がない正確な表現が好まれるようになりました。曖昧さを許容する文化が、少しずつ薄れているのかもしれません。
このように、私たちが生きてきた時代背景そのものが、言葉の解釈に大きな影響を与えているのです。良し悪しの問題ではなく、ただ「違う」という事実を、私はこの一件で痛感させられました。
現役時代の自分に伝えたい。コミュニケーションの落とし穴
この「8時10分前」問題は、私にとって単なる雑学ではありませんでした。現役時代の自分の姿を思い出し、深く反省するきっかけになったのです。
「言葉合わせ」を徹底してきた、という自負があったけれど…
私は長年、技術サポート部門と営業部門の間をつなぐ役割を担ってきました。営業はお客様の声をそのまま持ち帰り、技術サポートは解決策や手順に落とし込む――どちらも同じ課題について話しているのに、使う言葉や解釈が少し違うだけで、思わぬ誤解や行き違いが起きることがよくありました。
そこで私は、新しい案件やプロジェクトが始まる際には、必ず関係者を集めて「言葉の定義」を確認する場を設けてきました。いわば「言葉合わせ」の時間です。
たとえば「営業が言う『対応済み』とは、技術サポートで言うどの段階までを指すのか」「『導入済みのお客様』という表現は、契約が終わった段階なのか、実際に稼働が始まった段階なのか」といったことを、事前に明確にしておくのです。
こうした取り組みを続けることで、部門間の認識のズレを減らし、社内のコミュニケーションをスムーズにすることができました。
「伝えたつもり」が一番危ない。根本的な”当たり前”が違っていた衝撃
しかし、「8時10分前」の一件は、私のそんな自信を根底から揺るがしました。
私が徹底してきた「言葉合わせ」は、あくまで専門用語や業務上の言葉に限られていました。その土台となる「日常会話」や「基本的な概念」については、全員が同じ認識を持っていると信じ込んでいたのです。
「時間」という、誰にとっても普遍的で、疑う余地もないと思われた概念ですら、世代によってこれほどの解釈の違いがある。この事実は、私のコミュニケーション術に大きな穴があったことを示唆していました。
もしかしたら、あの時の若い部下への指示も、本当の意味では伝わっていなかったのかもしれない。「なるべく早めにお願い」という言葉は、私の中では「今日中」だったけれど、彼にとっては「今週中」だったかもしれない。「しっかりやっといて」という激励は、私にとっては「細部までこだわって」という意味でも、彼には「とりあえず終わらせて」と聞こえていたかもしれない…。
「伝えたつもり」「わかってくれているはず」。この思い込みほど、危険なものはありません。自分では丁寧なコミュニケーションを心がけてきたつもりでしたが、それはあくまで「自分の常識」という土台の上での話。その土台そのものが、相手とは違っていた可能性に、今更ながら気づかされたのです。背筋が少し、寒くなるような感覚でした。
定年後の今だからこそ。新しい「言葉の物差し」を手に入れる
定年を迎え、現役時代のような上下関係や利害関係から解放された今、私は非常にフラットな気持ちで人付き合いができています。だからこそ、この「言葉のズレ」の問題に、真摯に向き合いたいと思いました。
「自分の当たり前」を疑う勇気
まず大切なのは、「自分の当たり前は、他人の当たり前ではない」と常に意識すること。長年生きていると、どうしても自分の経験則や価値観が「常識」だと思い込んでしまいがちです。しかし、時代は変わり、文化は多様化しています。私の「常識」は、数ある価値観の一つに過ぎないのです。
この謙虚な姿勢こそが、新しいコミュニケーションの第一歩だと感じています。
確認を恐れない丁寧さが、信頼を生む
そしてもう一つは、「確認すること」を面倒くさがらない、恐れない姿勢です。
「念のため確認ですが、これは〇〇という意味で合っていますか?」
「〇〇時必着でお願いしたいのですが、大丈夫でしょうか?」
こんな風に、少しだけ言葉を足して確認する。これは、相手を信用していないからではありません。むしろ逆です。相手との間に誤解を生みたくない、お互いに気持ちよく物事を進めたい、という誠意の表れです。
特に、私のような年長者が若い世代と話すときには、この姿勢がより重要になるでしょう。上から目線で「俺の言うことを理解しろ」ではなく、「私のこの言い方で、ちゃんと伝わっていますか?」と問いかける。この双方向のやり取りこそが、世代の壁を溶かし、本当の意味での信頼関係を築いていくのだと信じています。
すれ違いを未然に防ぐこの小さな努力が、結果的に大きな安心感につながる。現役時代にこの境地に達していれば、もっと多くの人の心を掴めたかもしれないな、なんて少しだけ思ったりもします。
まとめ:あなたは「8時10分前」をどう伝えますか?
たった一言、「8時10分前」。 この言葉が、私に世代間のギャップの深さと、コミュニケーションの奥深さを教えてくれました。
これからの時代、ますます多様な価値観を持つ人々と共に生きていくことになります。そんな中で大切なのは、自分の物差しだけで相手を測るのではなく、相手の物差しを想像し、分からなければ素直に尋ねてみることなのかもしれません。
この記事を読んでくださったあなたは、「8時10分前」をどう解釈しましたか? そして、言葉のすれ違いでヒヤリとしたり、困ったりした経験はありませんか?
他にも「これって今は通じないの!?」と驚いた言葉や習慣があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのエピソードも、私にとって新しい『気づき』になります。
世代間のギャップを嘆くのではなく、笑い話にしたり、学びの機会に変えたりしながら、このブログで皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。
「雑記帳」では、これからも私が日々の生活で感じた「!」や「?」を、自分なりに掘り下げて綴っていく予定です。どうぞ、またお付き合いください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※コメント欄はページのいちばん下にあります。分かりにくくてごめんなさい。
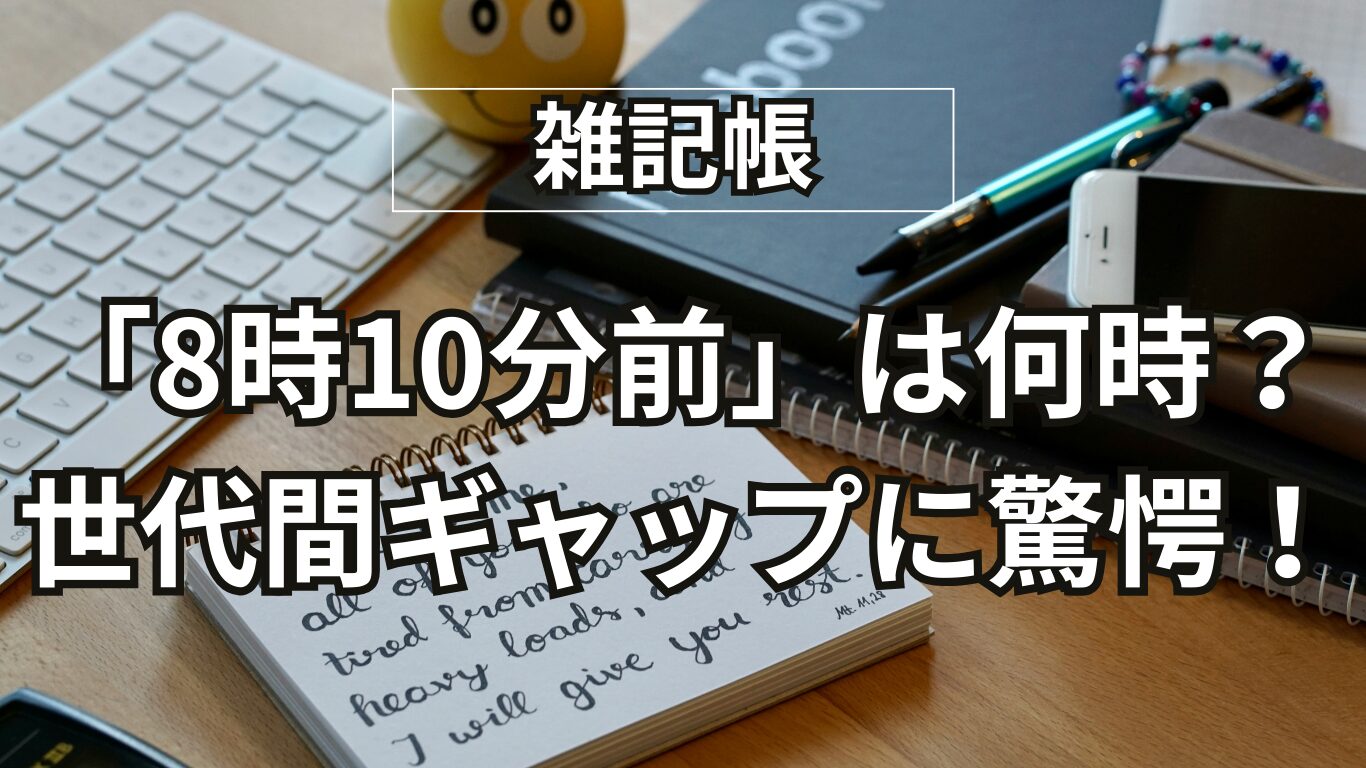

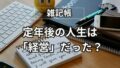
コメント