皆さん、こんにちは。てつやです。
長年勤め上げた会社を定年退職し、新しい挑戦の一つとして、フリーランスとして働きながら、このブログを運営しています。
これまで憧れつつも先送りにしてきたアレコレを「やってみた!」シリーズとして、ブログ開設に始まり、趣味の車中泊について綴っていますが、お楽しみいただけていますでしょうか。このブログ自体も、私にとっては大きな挑戦であり、日々の大切な張り合いになっています。
さて、今回も「雑記帳」のカテゴリで筆を進めます。
このカテゴリでは、「日々の生活の中で発見した些細な出来事」や「定年後の人生をどう豊かに生きるか」など、私自身の模索の中から得たヒントを思いつくままに綴っています。
▼こちらも「生き方」を考えるヒントになるかもしれません。
認知症になりやすい人、その意外な特徴とは
定年後の生き方を決めた一冊の本との出会い
そして今回は、これまでの記事の流れを汲んで、私の人生の羅針盤となった、もう一つの大切な言葉についてお話ししたいと思います。

「足るを知る」=我慢や妥協?定年前に抱いたネガティブな印象
それが「足るを知る」という言葉です。
この言葉、皆さんはどんなイメージを抱くでしょうか?
「現状に満足し、それ以上の欲を出さない」
「もうガツガツするのはやめて、ほどほどで生きる」
なんだか、「我慢」や「妥協」、あるいは「成長の停止」といった、少しネガティブで寂しい響きを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、私がこの言葉に深く向き合うことになったのは、定年後の今ではなく、定年を数年後に控え、これからの生き方を模索していた現役時代の終盤でした。当時の私もまた、この言葉にどこか後ろ向きな印象を抱いていた一人です。
しかし、前回ご紹介した本からの学びなどと結びつき、深く考えるうちに、この言葉が全く違う意味合いを持っていることに気づかされたのです。それは決して寂しい諦めの言葉ではなく、むしろこれからの人生を、より豊かで晴れやかなものにするための「強力な羅針盤」だったのです。
今回は、私が定年後の働き方・生き方を固める上で、いかにこの言葉に助けられたか。その心境の変化と、私なりの解釈についてお話しさせていただければと思います。
我々が駆け抜けた時代:常に「未来」のために生きてきた
私たちが社会に出た昭和の終わりから平成、そして令和へ。まさに激動の時代でしたね。誰もが「もっと豊かに、もっと便利に」と、坂道を駆け上がるようにして生きてきたように思います。
私自身を振り返ってみても、まさに「足りないもの」を埋めるための連続でした。
入社したての頃は、先輩に追いつくための知識と経験が足りない。結婚し、子供が生まれれば、家族を養うための給料が足りない。やがて、より広い家が欲しくなる…。
常に何かが「足りない」。 だから、目標を立て、計画を練り、努力する。 そうやって「足りない」を一つひとつ埋めていくことが、成長であり、生きることであり、社会的な成功だと信じて疑いませんでした。
それは、常に「未来の自分」のために、「今の時間」を投資する生き方だったのだと思います。今日の頑張りが、明日の豊かさにつながる。そう信じて、脇目も振らずに走り続けてきました。
もちろん、その生き方を後悔しているわけではありません。むしろ、その時代があったからこそ、家族との大切な思い出も、仕事で得た達成感も、そして今の自分があるのです。全力で駆け抜けた自分を、今は少しだけ誇らしく、そして愛おしくさえ思います。
人生の転機:定年後の働き方と生き方を模索した日々
そんな風にがむしゃらに走り続けてきましたが、50代も後半に差し掛かり、定年というゴールテープが目前に見え始めた頃、私の心には漠然とした不安と、そして同じくらいの期待が渦巻き始めました。
会社の看板がなくなった後、自分に一体何が残るのだろうか。 長年続けた仕事という大きな柱を失った時、自分は社会の中でどう立っていればいいのだろうか。
ただ趣味だけで日々を過ごす、いわゆる「隠居」生活は、どうも自分の性には合わない気がしていました。ありがたいことに体はまだ元気ですし、長年培ってきた経験や知識を、このまま眠らせてしまうのはもったいない。何か社会との関わりを持ち続けたい、という思いが強くありました。
そんな模索の末に、私は退職日の翌日からフリーランスとして働くという道を選びました。これまでとは違う形で、自分の裁量で、社会と関わり続けていこうと決意したのです。
会社のスケジュールで埋め尽くされていた手帳が、これからは自分の意思で埋めていく真っ白なキャンバスに変わる。そのことに、少しの不安と大きなワクワクを感じていました。
しかし、ここで一つ、大きな問いが生まれます。 「一体、どんな物差しで、これからの働き方や生き方を決めていけばいいのか?」
現役時代のように、会社の目標や昇進、給料アップといった分かりやすい指標はありません。自由であるということは、裏を返せば、全ての羅針盤を自分で用意しなければならないということでもあります。
そんな、人生の大きな交差点で道しるべを探していた時に、ふと私の心に飛び込んできたのが、冒頭で触れた「足るを知る」という言葉だったのです。
【私なりの解釈】「足るを知る」は人生後半を豊かにする羅針盤だった
最初は、やはりネガティブな印象でした。
しかし、前回ご紹介した本で学んだ「人生を豊かにする4つの時間」の話や、様々な先人たちの生き方に触れる中で、この言葉が持つ本来の奥深い意味に気づかされたのです。
それは、我慢や妥協などでは決してなく、「今、自分の手の中にあるものの価値に、深く気づくこと」。そして、その価値を「じっくりと味わい、大切に育てていくこと」でした。
視点を「外」の派手なものに向けるのではなく、「内」にある確かなものに向ける。 「ない」ものを数えて嘆くのではなく、「ある」ものを数えて感謝する。
この視点の転換は、私のフリーランスとしての働き方、そして人生後半の生き方に、確固たる軸を与えてくれました。
実践例①:働き方を変えた「深化・熟成」という考え方
例えば、「働き方」。 フリーランスとして、がむしゃらに仕事量を増やし、売上だけを追い求める生き方もできたかもしれません。しかし、私が選んだのは、自分の経験が本当に活かせる仕事、心から「やりたい」と思える仕事に絞り、一つひとつを丁寧にこなしていく働き方です。これもまた、「足るを知る」の実践だと感じています。量ではなく質を、拡大ではなく深化を大切にする働き方です。
実践例②:愛車フリードと古いキャンプ道具が教えてくれた本当の豊かさ
そして、この考え方は私の「趣味」の世界、特に車中泊において、より明確な形となって表れています。
定年を機に車中泊を本格化しようと考えた時、目の前には二つの選択肢がありました。一つは、思い切って何百万円もするような豪華な専用キャンピングカーを買うこと。もう一つは、今乗っている愛車、ホンダのフリードを車中泊仕様にカスタマイズして乗り続けること。
現役時代の私なら、迷わず前者を選んでいたかもしれません。しかし、私の心にあったのは「足るを知る」という羅針盤でした。
フリードは、普段の買い物や家族の送迎にも使える、とても便利な車です。趣味のために専用の車をもう一台持つのではなく、この便利な一台を最大限に活かせばいいのではないか。高価なものを「追加」するのではなく、今ある愛車の価値を「深化」させることこそ、今の自分らしい選択だと感じたのです。
このブログでもその過程を紹介していますが、キャンピングカービルダーへ車中泊仕様へ改装を依頼したり、自分の手で棚を作ったり、収納を工夫したりする時間は、まさに「自分の城」を築き上げるような喜びがあります。
さらに、この選択は思わぬ副産物をもたらしてくれました。キャンプギアとの再会です。
もちろん、車中泊を快適にするために、IHクッキングヒーターや電子レンジなど新たに買い足したものもあります。しかし、それ以上に私の心を豊かにしてくれたのは、物置の奥でホコリをかぶっていた古い道具たちを引っ張り出してきた瞬間でした。
若い頃に買ったケトルクッカー、子供たちがまだ小さかった頃の家族キャンプで使った三つ折りチェアやアルミロールテーブル…。どれも最新の軽量コンパクトなギアに比べれば、無骨でかさばるものばかりです。
でも、一つひとつ丁寧に磨き、メンテナンスをして再び火を灯した時、それらは単なる「古い道具」から「思い出の詰まった一軍ギア」へと生まれ変わりました。この道具たちが、再び活躍の場を得てどこか誇らしげに見えるから不思議です。
「ないもの」を追い求めて新しいものを次々と買うのではなく、「あるもの」を活かし、再び命を吹き込む。これこそが、「足るを知る」が教えてくれた、創造的で、きわめて前向きな楽しみ方なのだと実感しています。
まとめ:【60代からの人生戦略】「ないものねだり」から「あるもの探し」へ
「足るを知る」という言葉を、定年を迎える前に自分の中に落とし込めたことは、私の人生にとって本当に幸運なことでした。この羅針盤があるおかげで、フリーランスとしての新しい働き方にも、ブログという未知の挑戦にも、迷いなく踏み出すことができています。
向上心や「やってみたい」という気持ちがなくなるわけではありません。 ただ、その向上心の「ベクトル」が変わったのです。
これまでは、他人との比較の中で、「より上へ、より多く」を目指す、いわば「拡大・追加」の向上心でした。 しかし、これからは、自分の中にあるものに目を向け、「より深く、より丁寧に」味わう、「深化・熟成」の向上心を大切にしたいと思っています。
この記事を読んでくださっている、人生の先輩であり、同世代の仲間である皆さん。 私のように働き続けている方も、悠々自適の毎日を送られている方も、それぞれのステージで、これからの人生をどう豊かにしていくか、考えていらっしゃることと思います。
そんな時、この「足るを知る」という視点が、きっと一つのヒントになるはずです。
私たちはもう、「ないものねだり」をする必要はないのかもしれません。 これまでの人生で、すでにたくさんのものを手に入れてきたのですから。
これからは、その宝物を一つひとつ丁寧に取り出して、磨き、眺め、そして遊び尽くす「あるもの探し」の達人になりませんか?
「足るを知る」は、人生を諦めるための言葉ではありません。 自分自身を、そして自分の人生を、丸ごと肯定し、愛するための魔法の言葉です。
さあ、この心強い羅針盤を手に、一緒に、自分だけの豊かさに満ちた素晴らしい航海を続けていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆さんの「あるもの探し」のエピソードも、もしよろしければコメントで教えていただけると、とても嬉しいです。
それでは、また。
※コメント欄はページのいちばん下にあります。分かりにくくてごめんなさい。
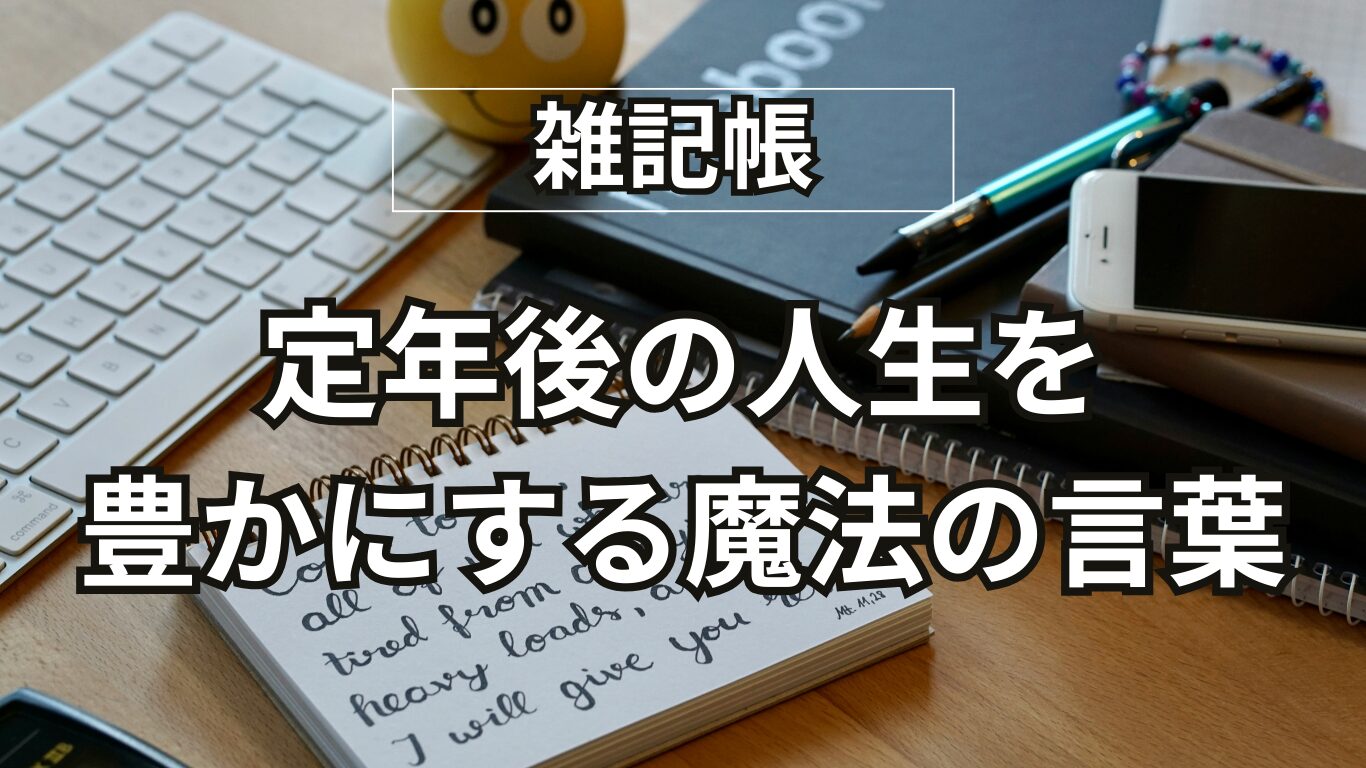


コメント