こんにちは!定年退職を機に、これまで先送りしてきたアレコレに挑戦し始めた、てつやです。
その挑戦の一つがこのブログ。第二弾の挑戦として車中泊を「やってみた!」シリーズもお届けしていますが、今回は少し趣向を変えて「雑記帳」として、私の価値観を根底から揺さぶった、ある言葉についてお話ししようと思います。
▼これまでの記事の一部をご紹介します
1年前に94歳で亡くなった岳父が80代の頃に認知症と診断され、妻と二人で介護や病気について必死で情報を集めていた時期がありました。そんな時、あるYouTubeチャンネルで出会った言葉が、私の心に深く、そして重く突き刺さったのです。
その言葉とは、認知症になりやすい人の特徴は「自分勝手な人」だというもの。
この言葉を初めて聞いた時、私は何の違和感も抱きませんでした。「だろうな、やっぱりわがままは良くないよな」と、むしろ深く納得したくらいです。しかし、その直後、私がこれまで「常識」だと思っていた「自分勝手」の意味が、全くの見当違いであることを知り、頭をガツンと殴られたような衝撃を受けました。
この記事は、私と同じように「自分は自分勝手ではない」と信じて生きてきた方にこそ、読んでいただきたい内容です。もしかしたら、あなたの「当たり前」も、少し変わるかもしれません。
腑に落ちたはずだった…「自分勝手=わがまま」という思い込み
岳父の認知症がわかり、藁にもすがる思いで情報を探していた私たち夫婦。そんな中で見つけたのが、認知症に関する情報を発信しているあるYouTubeチャンネルでした。
その動画で専門家の方が語った「アルツハイマー型認知症になりやすい人の特徴」が、「自分勝手な人」だったのです。
前述の通り、私はこの指摘に「なるほど」と深く頷きました。私の頭の中では、「自分勝手」イコール「わがまま」「自己中心的」という図式が完全に成り立っていたからです。周りの迷惑を考えず、自分の意見ばかりを押し通すような人は、当然、様々な軋轢を生むだろう。そんな生き方が、心身に良い影響を与えるはずがない。そう考えていました。
自分はこれまで、周りとの調和を重んじ、理不尽なことがあってもぐっとこらえ、真面目にやってきた。だからこそ、自分は「自分勝手」な人間ではないと信じて疑いませんでした。しかし、話はここで終わらなかったのです。
価値観の崩壊。本当の「自分勝手」が示す衝撃的な意味
動画の解説は、私の安直な納得を打ち砕くものでした。話の核心は、多くの人が本来の意味を誤解している「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿にありました。
私たちはこの言葉を「都合の悪いことから目を背け、耳を塞ぎ、口を閉ざす」という、処世術のように捉えがちです。しかし、その真意は全く逆でした。
- 見ざる:世の中の物事を、先入観なく自分の目でよく見て、本質を見極めなさい
- 聞かざる:人の言葉に真摯に耳を傾け、様々な意見を広く受け入れなさい
- 言わざる:その上で、自分の考えをしっかりと相手に伝えなさい
この本来の意味を知った時、全身に鳥肌が立ちました。そして、この三猿の教えに反する生き方こそが、本当の「自分勝手」なのだと、動画は語っていたのです。
つまり、認知症になりやすい「自分勝手な人」とは、
- (見ざる) 相手や物事をきちんと見極めようとせず、
- (聞かざる) 自分と違う意見や新しい情報に耳を貸さず、
- (言わざる) 波風を立てたくないという自分の都合で、意見や感情を伝える努力を放棄してきた人
のことだったのです。
これには、言葉を失いました。
動画では、認知症になる方には、かつて「古いしきたりの中で、家業と夫や子供たちのために自分を犠牲にしてじっと耐え忍んできた女性」の話が紹介されます。一見すると「自分勝手」とは程遠い、むしろ「我慢強い」「真面目」と評されるような方が少なくないというのです。
例えば、会社員時代の会議。若手が斬新なアイデアを出した時、心のどこかで「面白い」と思ったにもかかわらず、「前例がない」「リスクが大きい」と真っ先に口にしてはいなかったか。家庭では、妻の意見に心から納得していなくても、「ここで反論したら面倒だ」という一心で、話を合わせてしまったことはなかったか。
それらは全て、相手や組織を思っての行動ではなく、変化を恐れ、議論から逃げたいという究極の「自分勝手」だったのではないか…。 動画の解説は、そう私に問いかけているようでした。
私は「自分勝手」だったのか?定年後の生き方への影響
「自分は自分勝手ではない」――。その自信は、音を立てて崩れ去りました。
これまでの人生を振り返ると、胸が痛むほど思い当たる節があります。良かれと思って意見を飲み込んだこと、面倒な議論を避けるために「そうだね」と話を合わせたこと、自分のやり方に固執して、新しいやり方や若い世代の意見に耳を傾けなかったこと。
それら全てが、相手を思いやっての行動ではなく、ただ「自分が傷つきたくない」「面倒なことに関わりたくない」という、究極の「自分勝手」だったのではないか。そう思い至った時、愕然としました。
会社という組織に守られ、役職という鎧を身にまとっていた頃には、気づかなかった(あるいは、気づかないふりをしていた)自分の本当の姿。定年を迎え、全ての肩書がなくなった今、裸の自分として社会と向き合うことになり、この言葉の重みをひしひしと感じています。
このままではいけない。これからの人生、本当に「自分勝手」ではない生き方をしなければ。
まとめ:本当の「自分らしさ」で生きるために
「認知症になりやすいのは自分勝手な人」。この言葉に最初は安易に共感した私が、その本当の意味を知り、自身の生き方を深く内省することになった経緯をお話ししました。
この衝撃的な気づきは、定年後の私の生き方に大きな指針を与えてくれました。これからは、もっとしなやかに、もっと謙虚に、そしてもっと誠実に、人や社会と関わっていきたい。面倒でも、勇気がいることでも、きちんと見て、耳を傾け、そして自分の言葉で伝えていく。
このブログを通して私の挑戦や日々の気づきを発信することも、まさに「言わざる」を克服するための、私にとっての新たな一歩です。
それが、これからの人生を豊かにし、健やかに生きるための道だと信じています。この記事が、あなたにとっても、ご自身の生き方を振り返るきっかけになれば幸いです。
あなたはどう思われたでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
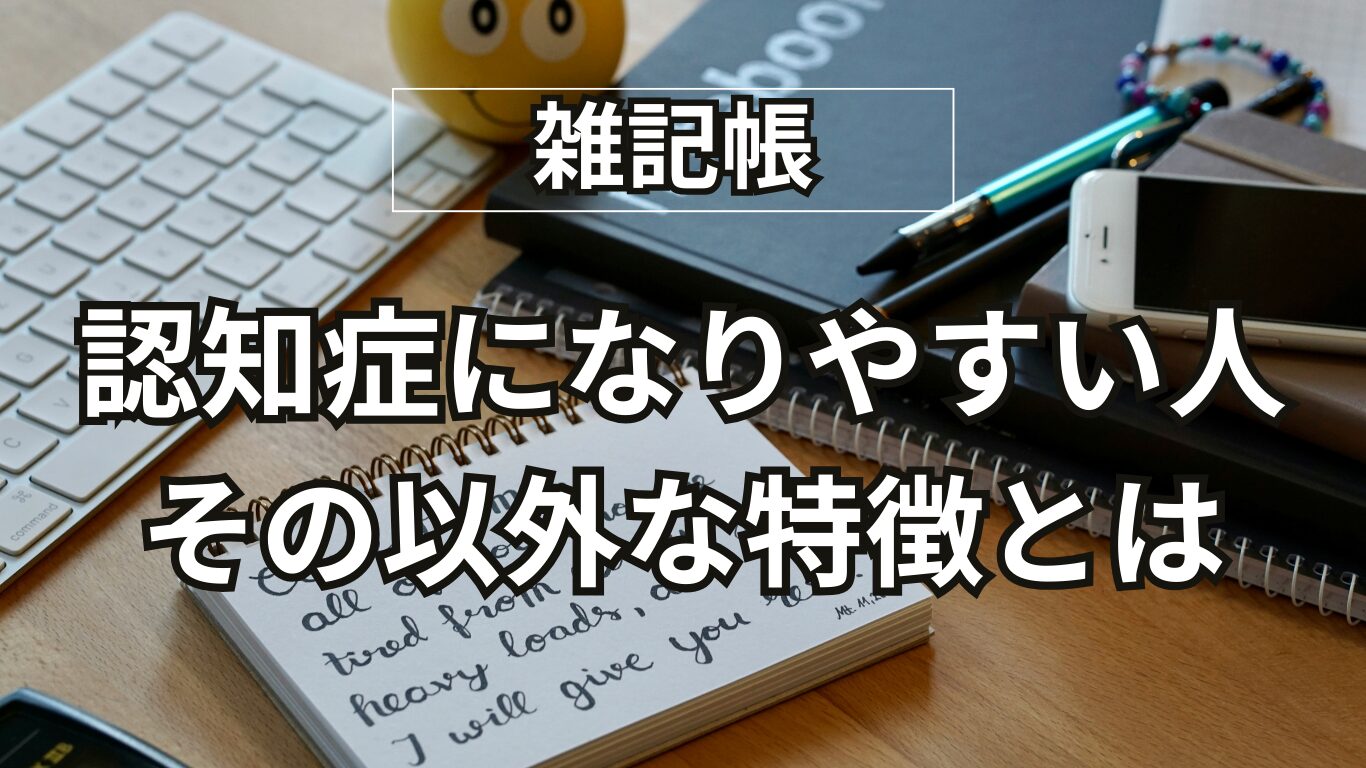
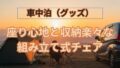

コメント