こんにちは!今年定年を迎え、第二の人生を謳歌中のてつやです。
実は、私と妻の結婚記念日は9月15日。かつては毎年必ず祝日だったので、ゆっくりお祝いするのが恒例でした。ところが、いつからか祝日ではなくなり、少し寂しく思っていたのです。
今年のカレンダーを見ると、9月15日は第三月曜日で「敬老の日」。何の疑いもなく「今年は結婚記念日が祝日だね」なんて妻と話していたのですが…。先日、日課のクロスワードパズルを解いていて、衝撃の事実を知ってしまいました。
今回は少し趣向を変えて、日常の中で「おや?」と思ったことを書き留める「雑記帳」カテゴリの記事をお届けします。
この記事では、クロスワードがきっかけで知った「敬老の日」と「老人の日」の違い、そして定年を迎えた今、「老人」という言葉に感じてしまう正直な気持ちを綴ってみたいと思います。
9月のカレンダーに並ぶ「敬老の日」と、私が最近その存在を知った「老人の日」について。この二つの日の違い、皆さんはご存知でしたか?

私たちの結婚記念日と「敬老の日」の思い出
本題に入る前に、少しだけ私の個人的な話をさせてください。 何を隠そう、私と妻の結婚記念日は9月15日です。
若い頃に式を挙げ、それから何十年。毎年この日が来ると、二人でささやかなお祝いをするのが恒例でした。昔は「敬老の日」といえば必ず9月15日で、国民の祝日でしたよね。だから、仕事の休みを気にすることなく、ゆっくりと食事に出かけたり、思い出の場所を訪れたりできたものです。
ところが、いつの頃からか「ハッピーマンデー制度」なるものが導入され、敬老の日が9月の第三月曜日に移動してしまいました。それ以来、9月15日が平日になる年も増え、結婚記念日だからといって特別に休みを取るのも気恥ずかしく、気づけば「今度の週末にでもお祝いしようか」と、当日を素通りすることが多くなっていました。
もちろん、お祝いする気持ちに変わりはないのですが、あの頃のように日本中が祝日ムードで、世の中全体がゆったりと流れる時間の中で記念日を迎えられた特別感は、少し薄れてしまったように感じ、一抹の寂しさを覚えていたのです。
きっかけは日課のクロスワードパズル「9月15日は何の日?」
そんな9月のある日のこと。私は朝食後、コーヒーを片手にスマホニュースのクロスワードパズルを解くのが日課です。頭の体操にもなりますし、知らなかった言葉に出会う楽しみもあります。
その日もいつものようにマスを埋めていました。そして、ある設問に手が止まります。
【タテのカギ】「9月15日は〇〇〇〇の日に」
私は何の疑いもなく「ケイロウ(敬老)」の4文字を思い浮かべました。しかし、すでに埋まっていた他のマスの文字と照らし合わせると、どうにも辻褄が合いません。
「あれ?おかしいな…」
首を傾げていると、ソファーでテレビを観ていた妻が「どうしたの?」と声をかけてきました。 「いや、ここの問題なんだけどね。『9月15日は何の日?』って、敬老の日じゃないのかな?」 「ええ?そうでしょう?今年のカレンダーもそうなってたじゃない」
妻の言う通り、今年のカレンダーでは9月15日が第三月曜日にあたり、確かに「敬老の日」と記されています。私もそれを見て、今年は結婚記念日が祝日だなと思っていたのです。
二人でうーん、うーんと唸りながら、他のマスからヒントを得て言葉を埋めていくと、答えが浮かび上がってきました。
「ロ」「ウ」「ジ」「ン」
……ろうじん? 老人の日?
「老人の日なんて聞いたことがないぞ」「敬老の日のことじゃないのか?」 夫婦そろって、頭の上に大きな「?」が浮かびました。長年当たり前だと思っていた常識が、ガラガラと音を立てて崩れていくような、不思議な感覚でした。
これはきちんと調べてみなければなるまい。 いつもの好奇心。私の「やってみた!」精神に、思わぬところから火が付いた瞬間でした。
調べてみて納得!「敬老の日」と「老人の日」は全くの別物でした
早速、パソコンを開いて調べてみることに。すると、驚くべき事実が次々と明らかになりました。「敬老の日」と「老人の日」は、名前が似ているだけで、根拠となる法律も、日付も、そしてその趣旨も異なる、全くの別物だったのです。
| 敬老の日 | 老人の日 | |
|---|---|---|
| 日付 | 9月の第3月曜日 | 9月15日 |
| 根拠法 | 国民の祝日に関する法律(祝日法) | 老人福祉法 |
| 位置づけ | 国民の祝日 | 記念日 |
| 趣旨 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う | 老人の福祉への関心と理解を深め、老人自身が生活向上に努める意欲を促す |
祝日としての「敬老の日」(9月第3月曜日)
まず、私たちに馴染み深い「敬老の日」。こちらは「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で定められた、れっきとした国民の祝日です。
- 日付: 9月の第3月曜日
- 趣旨: 「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」
もともとは、兵庫県のある村が始めた「としよりの日」が起源とされ、それが全国に広まり、1966年に国民の祝日として制定されたそうです。制定当初から2002年までは、日付が9月15日に固定されていました。私たちが「9月15日=敬老の日」と記憶しているのは、このためですね。
記念日としての「老人の日」(9月15日)
一方、クロスワードパズルの答えだった「老人の日」。こちらは「老人福祉法」という法律で定められた「記念日」です。祝日ではないので、カレンダーに赤く記されることはありません。
- 日付: 9月15日
- 趣旨: 「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」
さらに、この「老人の日」から一週間、9月21日までが「老人週間」と定められています。こちらの目的は、お祝いムードの強い「敬老の日」とは少し異なり、社会全体で高齢者福祉について考え、高齢者自身もいきいきとした生活を目指すことを促す、といった啓発的な意味合いが強いようです。
なぜ2つの日が生まれたのか?背景には「ハッピーマンデー制度」
では、なぜこのような分かりにくい状況になってしまったのでしょうか。 その鍵を握るのが、私たちの結婚記念日の思い出にも関わってくる「ハッピーマンデー制度」でした。
ハッピーマンデー制度とは、ご存知の通り、一部の国民の祝日を特定の月曜日に移動させることで土・日・月と続く三連休を作り出し、余暇を過ごしやすくしようという目的で導入された制度です。
- 2000年~: 成人の日(1月15日 → 1月第2月曜日)、体育の日(10月10日 → 10月第2月曜日)が移動。
- 2003年~: 海の日(7月20日 → 7月第3月曜日)、そして敬老の日(9月15日 → 9月第3月曜日)が移動。
この2003年の祝日法改正によって、私たちの結婚記念日である9月15日は、「敬老の日」という祝日の看板を下ろすことになったのです。
しかし、長年にわたって親しまれてきた「9月15日」という日付を記念日として残したい、という国民の声も根強かったようです。そこで、この動きに応える形で、2002年に「老人福祉法」が改正され、新たに9月15日を「老人の日」、そして続く一週間を「老人週間」として定められることになりました。
つまり、祝日だった「敬老の日」が月曜日に“引っ越し”をし、がら空きになった9月15日という“跡地”に、今度は記念日として「老人の日」が制定された。 これが、事の真相だったのです。
「なるほど、そういうことだったのか!」 調べ終えてスッキリした私は、思わず「へぇ~」と声が出てしまいました。隣で聞いていた妻も「そうだったのねぇ。じゃあ、これからは結婚記念日は『老人の日』でもあるのね」と笑っています。さっきまでモヤモヤしていた疑問が一気に晴れて、夫婦そろって、とてもスッキリとした気持ちになりました。
「老人」という言葉の響きに、まだ慣れない自分がいる
スッキリはしたものの、私の心には、もう一つ別の感情が芽生えていました。 それは、「老人」という言葉に対する、何とも言えない“ざらつき”のような感覚です。
クロスワードの答えが「老人の日」だと知った時、そしてその意味を調べている時、私の頭の片隅には、常にこの違和感が付きまとっていました。
今年、定年を迎え、孫もいる身です。世間的に見れば、まごうことなき「老人」のカテゴリーに入る年齢なのでしょう。それは、頭では理解しています。 しかし、いざ「老人」という言葉を自分自身に向けられると、どこか他人事のように感じてしまう。「いやいや、自分はまだそんな歳じゃない」と、心の中で首を横に振っている自分がいるのです。
辞書で引いた「老人」の意味
気になったので、辞書で「老人(ろうじん)」という言葉を引いてみました。
| 辞書 | 記述の概要 |
|---|---|
| コトバンク(デジタル大辞泉) | 年をとった人。年寄り。老人福祉法では、老人の定義はないが、具体的な施策対象は 65歳以上を原則としている。 |
| 精選版 日本国語大辞典 | 年老いた人。年寄り。老者。 |
非常にシンプルです。そこにネガティブな意味合いは含まれていません。 ただ、「年をとった人」という事実が示されているだけです。
それなのに、なぜ私はこんなにも違和感を覚えてしまうのでしょうか。 おそらく、これまで自分が無意識のうちに「老人」という言葉に対して、どこか「衰え」や「弱さ」「社会の一線から退いた人」といった、少しネガティブなイメージを抱いてしまっていたからなのかもしれません。
現役で働いていた頃は、「老人」とは自分とは違う、遠い存在だと思っていました。しかし定年を迎え、いざ自分がその立場になってみると、気持ちは昔と何ら変わっていないことに気づきます。まだまだやりたいこともあるし、学びたいこともある。ブログや車中泊といった新しい挑戦に胸を躍らせている今の自分と、「老人」という言葉の持つ静的なイメージが、どうにも結びつかないのです。
年齢を重ねることは、決してネガティブなことではない
しかし、今回のことをきっかけに、色々と考える良い機会になりました。 「老人」という言葉の響きに戸惑う一方で、年齢を重ねてきたからこその今の自分があることも事実です。
若い頃のような体力はないかもしれません。記憶力も少しずつ怪しくなってきました(笑)。 それでも、これまでの人生で培ってきた経験や知識は、何物にも代えがたい財産です。若い頃には見えなかったものが見えるようになったり、些細なことに幸せを感じられるようになったり。失ったものばかりではなく、得たものもたくさんあるはずです。
読者の皆さんは、ご自身の年齢を重ねることについて、どのように感じていらっしゃいますか?
「老人の日」の趣旨には、「老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」という一文がありました。 これはまさに、今の私へのエールのように聞こえます。
「老人」というレッテルに囚われるのではなく、一人の人間として、これからも自分の生活を、人生を、より豊かにしていく努力を続けなさい。そう言われているような気がします。
言葉の響きに慣れるには、もう少し時間がかかるかもしれません。 でも、これからは「老人」という言葉を聞いたら、「敬老の日」の“敬われる”だけの存在ではなく、「老人の日」が促すような“自らの生活向上に努める”アクティブな存在なのだと、胸を張って言えるようになりたい。そんな風に思うようになりました。
まとめ:日常の「?」は、新しい発見の宝庫
今回は、日課のクロスワードパズルという本当に些細なきっかけから、「敬老の日」と「老人の日」という大きな違いを知ることができました。
- 敬老の日(9月第3月曜日):祝日。おじいちゃん、おばあちゃんに感謝し、長寿をお祝いする日。
- 老人の日(9月15日):記念日。高齢者福祉に関心を深め、高齢者自身もいきいきと生きることを目指す日。
長年の「9月15日=敬老の日」という思い込みが、ハッピーマンデー制度によって複雑に形を変えていたことを知り、まさに目から鱗が落ちる思いでした。
そして、この発見は同時に、定年を迎えた自分自身が「老人」という言葉とどう向き合っていくか、という内面的なテーマにも繋がりました。まだ少し複雑な気持ちはありますが、これもまた、新しい人生のステージに進んだからこその気づきなのでしょう。
このブログのテーマは「やってみた!」ですが、何も大それたことばかりが挑戦ではありません。日常の中でふと生まれた「なぜ?」「どうして?」をそのままにせず、自分の手で調べてみる。これも立派な「やってみた!」の一つだと、今回改めて感じました。
私たちの結婚記念日である9月15日。 これからは、「敬老の日じゃなくなった記念日」として少し寂しく思うのではなく、「老人の日、つまり、私たち自身がこれからも元気に生活向上を目指すことを誓う記念日だね」と、妻と笑い合いたいと思います。
皆さんの周りにも、当たり前だと思っていることの中に、意外な発見が隠されているかもしれませんよ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
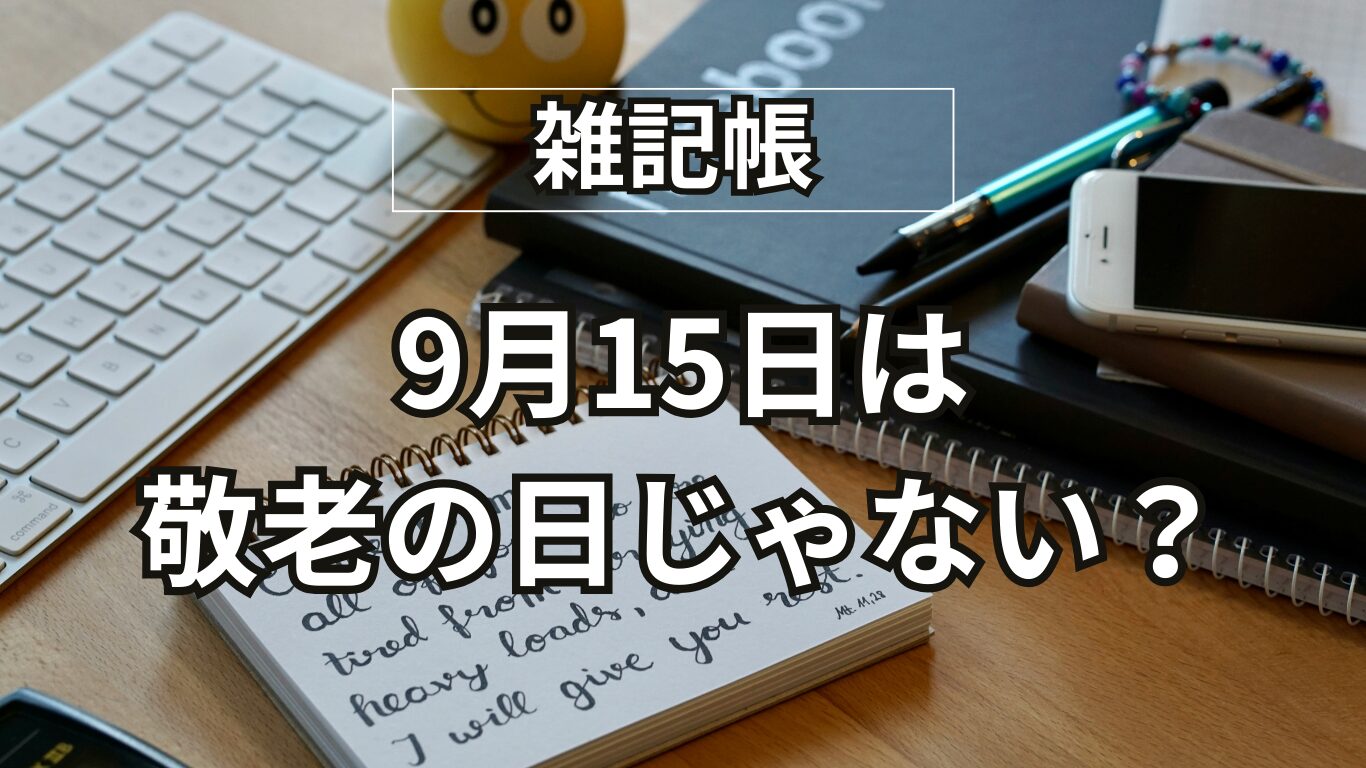
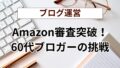
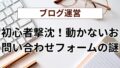
コメント